2023年にnatural tableさんのもとでオンラインセミナーを行いました。僕がこれまで携わってきたマッサージ関係、特に《触れること》をテーマにしたセミナーです。終わってから、そのままにしていたのですが、最近のA Iの広まりを聞いて、当日の録音データの整理をお願いしてみました。出てきたものが、今回、ご紹介する「触れることについて2023 記録」です。
出てきたのをみて、「これがA Iなんだ」と思いました。読んでみて表現が少々偉そうな感じがするのは、A Iさんだからです。《触れること》に関心がある方にご覧になっていただければと思います
本講義録の目的
この文書は、中安一成による講演「触れることについて2023」の要点を構造的に整理し、示された洞察を読者が再確認し、実践に活かすためのリソースとして作成されたものです。そのため、いわゆる“文字起こし”ではなく、講演が示す概念とその内容を、一般の方にも明確に伝わるように再構成しています。
1. 導入
本講演は、「触れる」という誰もが日常的に経験する普遍的かつ根源的な行為を、単なる感覚論に留めることなく、再現性と共有の可能性を持つ専門的な「技術論」として掘り下げる試みです。ただし、その内容は施術者やセラピストはもちろん、人と関わるすべての人にとって、その関わりの質を見直すための提案となっています。
2. 前提:なぜ「触れること」を探求するのか
具体的な技術論に入る前に、講演者は自身の探求の原点と、その背景について述べました。これは、技術が単なる手順の模倣に陥ることを防ぎ、その背景にある意味を理解するための土台となります。
講演者の探求は、少年時代から持っていた「世界の仕組みを知りたい」という根源的な問いから始まりました。
成人後に、その広大な問いに対するアプローチとして選んだのが「身体」でした。講演者は身体を、それ自体が世界の構造を反映した小さな縮図(ミクロコスモス)であると捉えたのです。この視点に立つことで、講演者は次のような考えに至りました。
「体に触れることは、世界に触れること」
「体を知ることは、世界を知ること」
この考え方は、本講演が単なるマッサージ技術の解説に留まらない、より広範な内容を持つことを示しています。
この前提に立ち、講演者は参加者に対して、本講演の内容を絶対的な正解としてではなく、一つの視点として受け止めてほしいと、以下の注意点を伝えました。
・ 自身の経験に基づく一つの参考意見であること
講演内容は講演者自身の経験から得られた洞察ですが、それが唯一の正解ではないことを強調しました。
・ 多様な可能性の尊重
マッサージやボディワークには多くの考え方や体系があり、それぞれの技術やアプローチには独自の価値があります。そのためそれぞれの考え方や体系は尊重されるべきであり、参加者自身の経験や考え方も尊重してほしいと呼びかけました。
このように、これから展開される具体的な技術論が、より深く、多角的に理解されるための準備が整えられました。
3. 「触れること」の技術論:内側と外側の技術

本講演の核心的なフレームワークは、「触れること」を「内側の技術」と「外側の技術」という二つの側面に分けて捉えるという独自の視点にあります。これらは独立したものではなく、二つの技術が統合されることで初めて、真に心身に響く質の高い「触れること」が実現します。
講演者は、感覚や体験といった主観的なものを言葉にし、その言葉に基づいて再現性を確保することで、漠然とした「触れる」という行為が客観的に共有可能な「技術」へと昇華されると説明しました。このプロセスを通じて、マッサージ教育の現場で多くの人々と概念を共有し、探求を深めてきたのです。
講演者は、マッサージの土台は「触れることのクオリティ」にあると主張します。例えば、「どんなに巧みな手技を用いても、触れるクオリティが低ければ心身には響かない。逆に、非常にシンプルな手技であっても、触れるクオリティが高ければ、それは深く心身に届き、十分な効果を発揮する」という対比は、この概念を明確に示しています。
この「触れることのクオリティ」を構成する二つの技術は、以下のように定義されます。
| 技術の側面 | 定義と特徴 |
| 内側の技術 | 心持ち、意識の向け方、感覚といった、施術者の内的な状態を指す。動画や画像、書籍などでは客観的に伝えにくい、主観的で精神的な側面を持つ。 |
| 外側の技術 | 具体的な手の使い方、姿勢、動き方など、客観的に観察・学習できる物理的な所作を指す。動画や画像、書籍などで明確に伝えられ、再現性が高い。 |
これら二つの技術は、車の両輪のように機能します。本講演ではまず、全ての土台となる「内側の技術」から、その具体的な内容を深く掘り下げていきます。
4. 内側の技術:意識と心の在り方
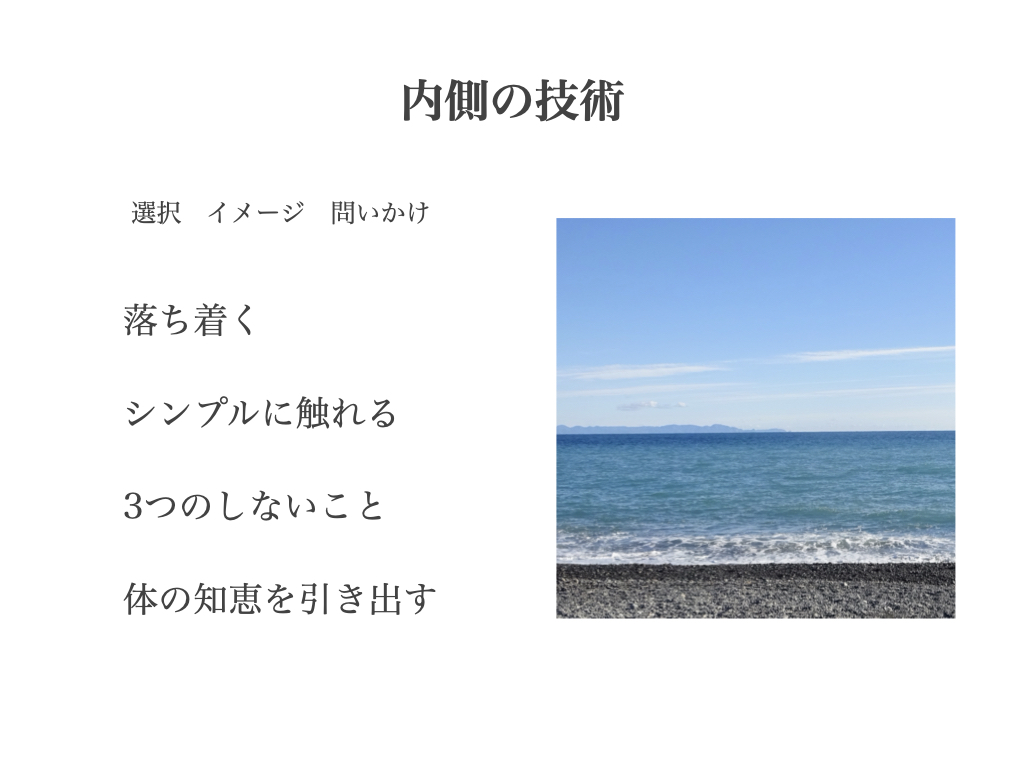
「内側の技術」とは、施術者の精神的な状態や意識の向け方といった、目には見えない内面的なアプローチを指します。
これは後述する「外側の技術」の効果を決定づける、いわばOSのような基盤となるものです。講演者は、この内的な状態を意識的に整え、磨き上げることの重要性を説き、4つの具体的な技術を提示しました。
4.1 落ち着くこと
「落ち着く」という状態は、単なる心構えではなく、能動的に作り出すことのできる技術です。そのための具体的な要素として、以下の4点が挙げられました。
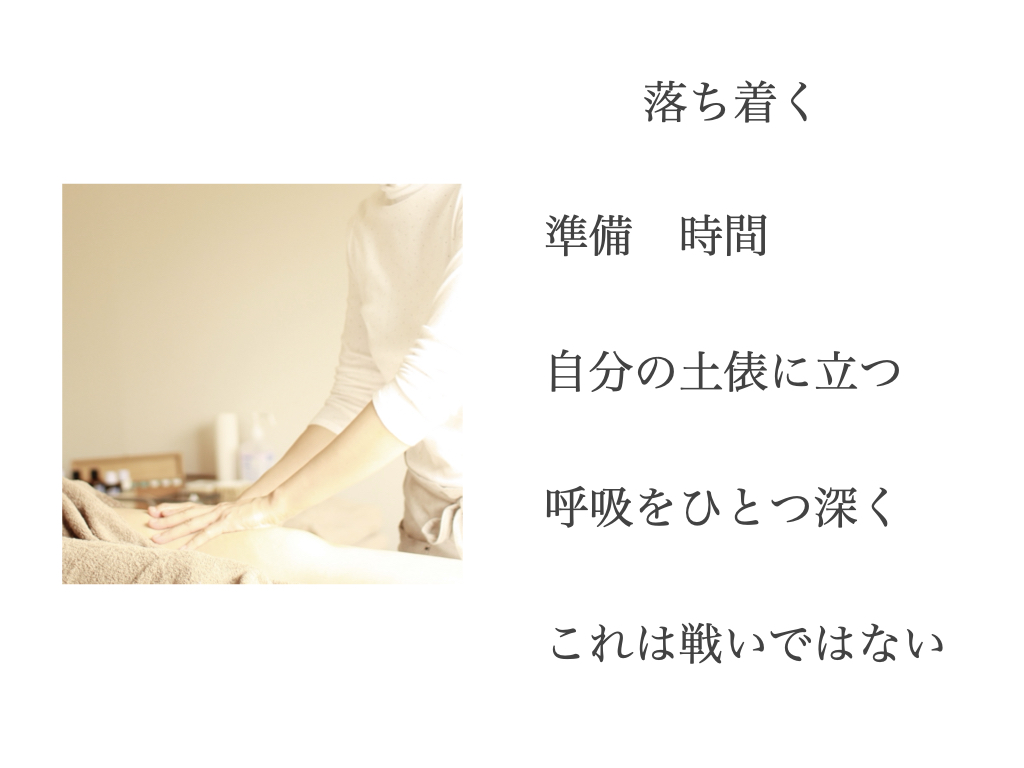
・ 十分な準備と時間的余裕
施術スペースを整えるといった物理的な準備と時間的な余裕は、自身の能力を最大限に引き出すための基本条件です。焦りや準備不足は、そのまま触れる手の質に現れます。
・ 自分の土俵に立つ
施術者自身の専門領域を明確に認識し、その範囲で責任を持って関わることが重要です。
例えば、専門外の医学的な質問には、正直に専門家(医師や薬剤師、そのほかの専門家)への相談を促す「交通整理」を行い、自身はマッサージという専門領域で最大限のサポートを提供することに集中します。
・ 呼吸を一つ深くする
受け手(クライアント)よりも、常に一つ深い呼吸を意識することで、自身の存在を安定させ、場に落ち着きをもたらすことができます。呼吸は自身のエネルギー状態を反映するバロメーターです。
・ 「戦いではない」と認識する
「凝りをなくしてやる」「リラックスさせてやる」といった闘争的な意識は、無意識のうちに力みや対立のエネルギーを生み出します。触れることは、受け手と調和し、共鳴するプロセスであり、決して戦いではありません。
4.2 シンプルに触れること
私たちは日常、何かしらの目的や理由を持って他者に触れることがほとんどです。しかし、マッサージの場では、その目的意識を一旦手放し、「ただ、シンプルに触れる」ことが求められます
これは目的(例:リラックスしてほしい、凝りを和らげたい)を否定するのではなく、一時的に関わり方として「保留」するということです。
その期待や目的を一旦横に置き、純粋な「好奇心(これって何だろう?)」を持って相手の体に触れること。この先入観のない探求的な姿勢こそが、あらゆる技術の第一歩となります。
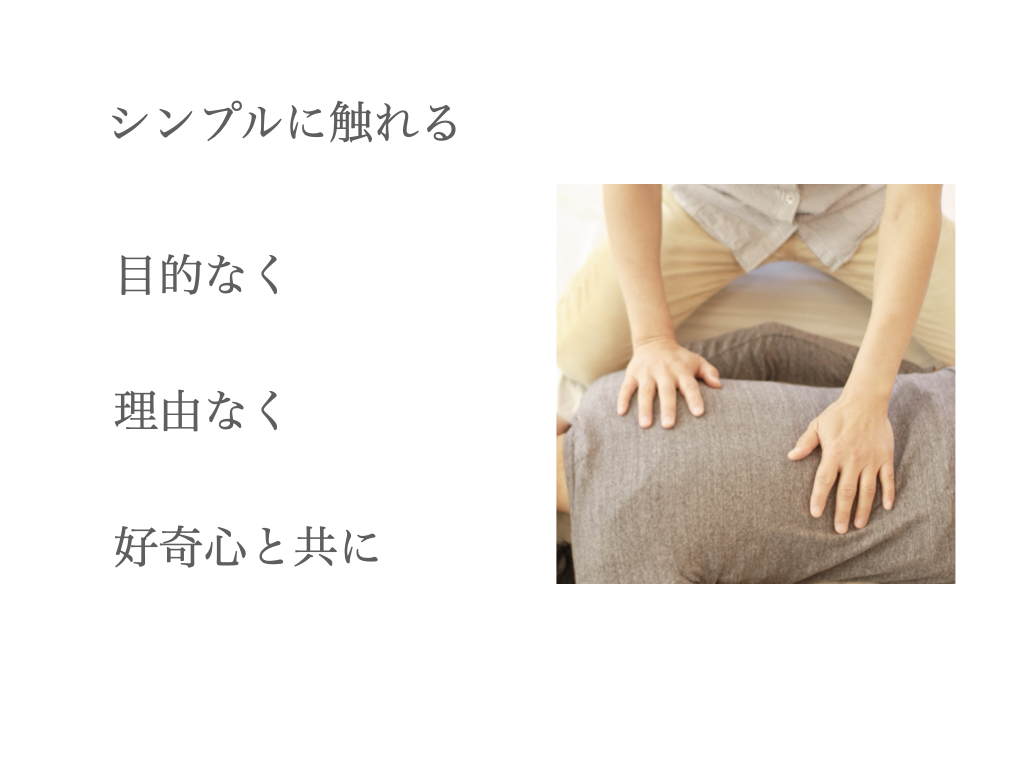
4.3 3つの「しないこと」(判断の保留)
シンプルに触れることを実践するために、講演者は「しないこと」として、3つの要素を意識的に、一時的に手放すことを提案します。これを「判断を保留する」という概念で説明しました。
「判断を保留する」とは、判断しないことではなく、技術の進行の中で、評価や比較、期待といった判断を一時的に横に置くことです。
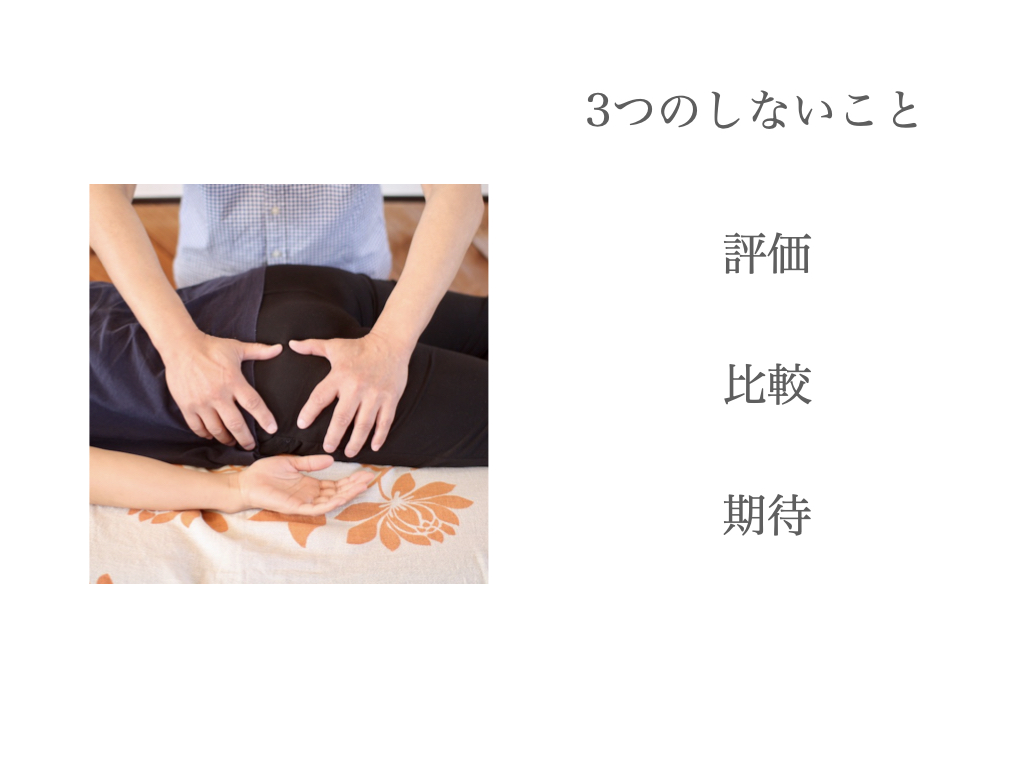
・ 評価しない
「自分の技術は正しいか」「この体の状態は良いか悪いか」といった知的な、評価的な思考を一旦停止します。
・ 比較しない
「他の人と比べてどうか」といった比較の視点を手放します。
・ 期待しない
「こうすればこうなるはずだ」という結果への期待や予測を一旦横に置きます。
この実践例として、「妊婦さんのお腹をパートナーが触れる」というケースが紹介されました。「元気な子が生まれますように」といった様々な思いは自然なものですが、時には、その思いが手の表情に力みとして現れることがあります。
そこで講演者は、「ポカンとした状態」で触れることを勧めます。これは、雄大な自然(海、山、大きな木など)を前にして、思わず言葉を失ってしまうような、思考が停止した状態に近い感覚です。この判断のない、ただ在るがままを受け入れる状態が、最も繊細で深い触れ方を生み出します。

4.4 体の知恵を引き出す
私たちの体は、意識の持ち方一つでその反応を変化させる「知恵」を持っています。「巨大な岩を持とうとする時の手」と「生まれたての赤ちゃんを抱こうとする時の手」では、意識を向けた瞬間に手の表情(筋肉の緊張度や形)が全く異なるものになる、という例がその証左です。この体の知恵を意図的に引き出すためのヒントとして、以下の3つが挙げられました。
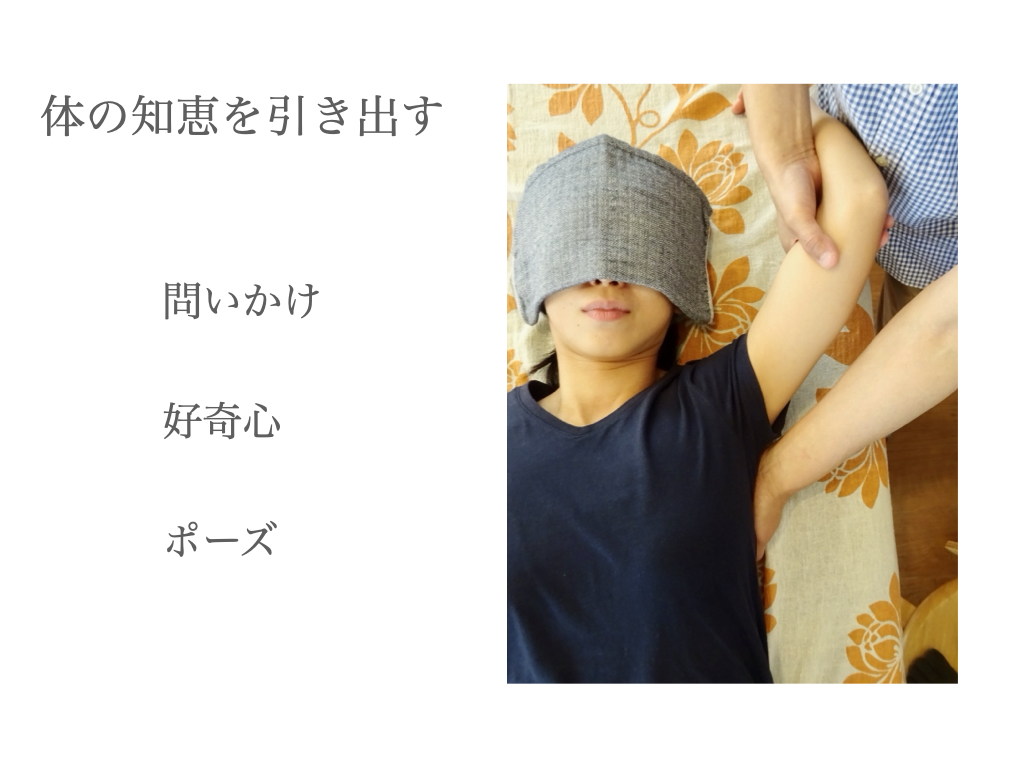
・ 問いかけ
頭で答えを出すのではなく、自分自身の体に問いかけ、「体からの応答を待つ」アプローチです。
「柔らかな手ってどんな感じ?」、「体を安心感と共に受け取るって、どんな感じだろう?」と問いかけると、頭で考えるよりも先に、手が最適な形や触れ方、圧を見つけ出します。
・ 好奇心
「この人の背中はどうなっているんだろう?」という純粋な興味は、手の感覚を増幅させます。知りたいという欲求が、無意識のうちに手の動きをより繊細で的確なものへと最適化していくのです。
・ ポーズ(小休止)
手技と手技の間に意識的にわずかな時間、「間」を置きます。これには二重の意味があります。
- 受け手にとって: 刺激を内面化し、深く「感じるための時間」となります。体は刺激の量よりも、感じた体験で変わります。
- 施術者にとって:自身を一旦リセットし、心身がニュートラルな状態に戻るための時間となります。
これらの内的なアプローチは、単独で完結するものではありません。次章で解説する具体的な外側の技術と一体となって、初めてその真価を発揮するのです。
5. 外側の技術:再現可能な身体の所作
「外側の技術」とは、客観的に観察し、学習することが可能な、具体的な身体の動きや姿勢、手の使い方を指します。これらは前述した「内側の技術」という精神的な土台の上で実践されることで、単なる物理的な動作を超え、心に響く表現へと昇華されます。
外側の技術としては、さまざまなマッサージの種類があります。そこで今回は、やや内側の技術に近く、いろいろなマッサージ技術に応用できるものをご紹介します。

5.1 感覚の言語化:技術への昇華
技術の探求と共有において、最も重要なプロセスの一つが「感覚の言語化」です。
感じたことを感じたままにせず、言葉にすることで初めて、その体験は客観化され、他者と共有し、再現可能な技術となり得ます。講演者は、感覚を丁寧に吟味し、言葉にするためのステップとして以下を提示しました。
・ すぐに言語化しない
感じた直後に言葉にしようとせず、まず「間」を置きます。
・ 体験の中に入る
言葉にする前に、その感覚の体験そのものに深く浸ります。
・ 後から思い出す
時間を置いてから体験を思い出すことで、本質的な感覚と、その本質に基づいた法則性が浮かび上がってきます。
・ 体験の意味を問いかける
その体験が何を語っているのかを、自分自身に問いかけます。
・ 書き留める(メモにする)
浮かび上がってきた言葉を書き留めることで、感覚が定着し、明確になります。
5.2 手の使い方
効果的な手の使い方に関する3つの要点は、いずれも力ではなく、意識と形の調整にあります。
・ 手の表情に気づく
意図を持たないニュートラルな手の状態を、講演者は「はんぺんの手」という独特の言葉で表現します。ここで講演者は、自身の出身地で親しまれていた「黒はんぺん」をイメージしていると補足しました。
・ 黒はんぺんとは
一般的に想像される白くふわふわしたものではなく、魚のすり身が凝縮された「ペタッとした」質感の黒はんぺんこそが、講演者の意図する「どこにも焦点が合っていない柔らかなフラットな手」の的確な比喩となります。
もしこのイメージが湧きにくい場合は「柏餅の手」でも良いとされ、いずれも指先に力が集中せず、手のひら全体で受け手の体をそのまま受け入れるための基本形を指します。
・ 手の中心から触れる
指先からではなく、手のひらの中心(労宮)を意識して触れることで、より安定し、手全体で深く受け手と繋がることができます。
・ 手を大きく使う
実際の手の大きさ以上に、受け手に「大きな手で包まれている」と感じさせることが重要です。これは、5本の指を固定せず、柔らかな手で受け手の体のカーブに沿って自由に開閉させ、接触面積を最大化することで実現します。
5.3 触れ方と言葉の選択
触れる際の意識と、その意識を導くための「言葉の力」は、動きの質に明らかな変化を生み出します。
・ 体温を感じる
受け手の体に触れる際、その体温を「その人の存在そのもの」として感じる意識を持つことで、触れ方はより丁寧で敬意のこもったものになります。
・ 言葉で動きを導く
自分がこれから行う動きをどのような言葉で定義するかが、手の表情を決定します。
・ たとえば
「握る」ではなく「包む」:「包む」という言葉には、「守る」「大切にする」というニュアンスが含まれ、手は自然と安全で優しい表情になります。
「とらえる」ではなく「束ねる」:たとえば「腰から全身を束ねて揺らす」です。「束ねる」には、腰を単なる部分としてではなく、上半身と下半身を繋ぐ中心点として捉える視点を生み出し、「束ねる」という表現で身体の上下を繋ぎ、より全体的で調和の取れた動きを導き出します。
5.4 位置、姿勢、動き方
施術者自身の身体の使い方は、技術の安定性と効果に直結します。また動きの質を高める比喩的な表現も紹介されました。
・ 位置と視線
常に受け手の正面に立ちます。目は、部分に集中する硬い視線ではなく、「全体を見る」柔らかい視線を保ちます。
・ 受け手との距離
受け手との距離は、「自分のものという距離」、すなわち赤ちゃんを抱っこするように、最も楽に安定して保持できる範囲で行うのが基本です。これにより、余分な力みがなくなり、全身で関わることができます。
・ 身体の基本形
「腰は近づき、頭は離れる」という原則を意識します。これにより、体幹が安定し、自然と「肘を柔らかく伸ばす」ことができ、身体の中心からの効率的な力の伝達が可能になります。
・ 重さと共に動く
受け手の手や足などの手や足などの体の重さを感じ、その重さと一体となって動くことで、調和と信頼感が生まれます。
・ 楽しげに行う
深刻にならず、楽しむ意識を持つことで、体は自然とリラックスし、動きは全体的でリズミカルになります。
・ 羽衣をまとうように動く
あたかも薄い羽衣をまとっているかのように動くイメージは、周囲の空間と調和し、流れるような一体感のある動きを生み出します。
6. 実践の心得と結論:「あの感じ」をつかむために
これまで学んだ「内側の技術」と「外側の技術」を統合し、実際の臨床や日々の実践の場で活かすための心構えとして、講演者は実践的かつシンプルな方法を提示しました。
まず、「うまくいかない時」の具体的な対処法として、部分的な修正ではなく、全体的なリセットの重要性を説きました。
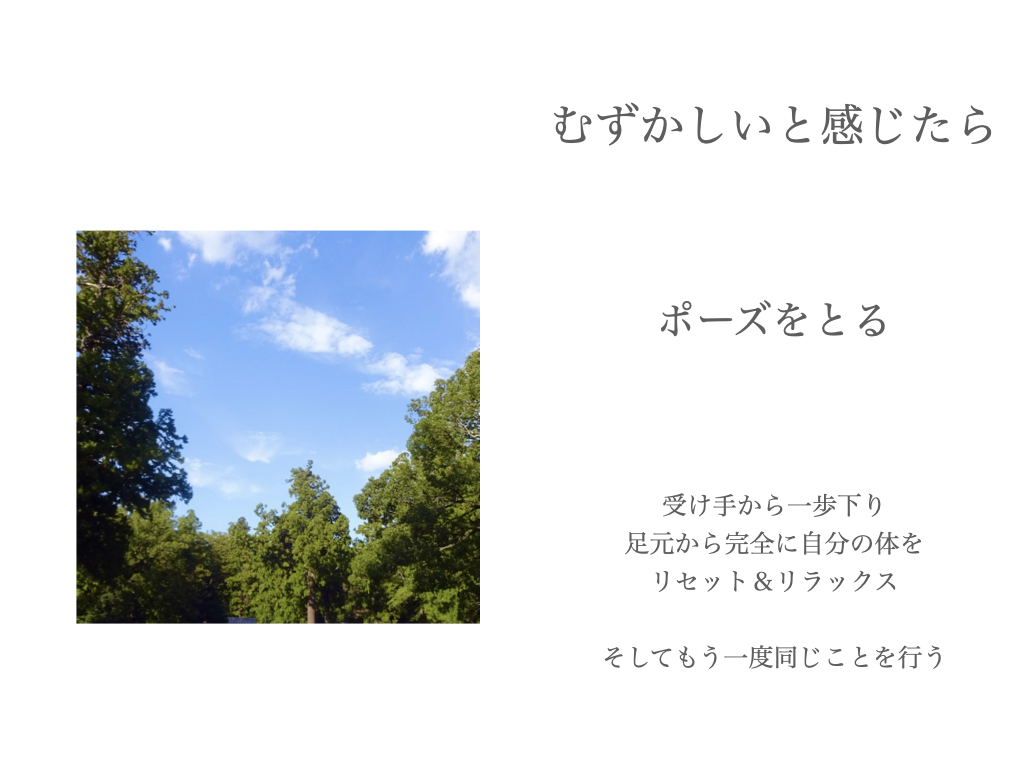
6.1 うまくいかない時の対処法
- 一旦、相手の体から、完全に手を離す。
- さらに一歩下がり、物理的な距離を取る。
- 自分の足元から意識を始め、全身をリセットし、リラックスする。
- 新しいアイデアがなくても、もう一度、同じことをやってみる。
このプロセスは、思考や上半身のみといった部分的な修正に陥ることを防ぎ、全身の状態をリセットすることで、状況が好転する可能性を飛躍的に高めます。
そして、講演の結論として、2つの提案が語られました。
6.2 おしまいに、2つの提案 シンプルであることと魔法の言葉
1 シンプルさの追求
「うまくいっている時は、シンプルで簡単である」という原則が示されました。技術の習熟とは、複雑なことを複雑なまま行うのではなく、いかに努力なく、シンプルに、そして単純に行えるかを探求するプロセスです。常に単純化を目指す姿勢こそが、真の熟達への道となります。
2 魔法の言葉「あの感じでやってみよう」
これは、本講演で受け取った数多くの知識や体験を、一つ一つ理屈で思い出すのではなく、全体として統合し、直感的に再現するための究極のキーワードです。
研修で得た感覚、心地よかった時の記憶、それら全てを「あの感じ」という言葉に集約し、自分自身に呼びかけます。「あの感じでやってみよう」、この言葉は、知識と体験を瞬時に統合し、身体の知恵を引き出すためのスイッチとなる魔法の言葉、「内側の技術」の究極形と言えるでしょう。
この講演は、参加者一人ひとりにとって、「触れること」という日常的な行為の奥深さを再発見し、日々の実践をより豊かで意味のあるものにするための指針として示しました。
おわり









